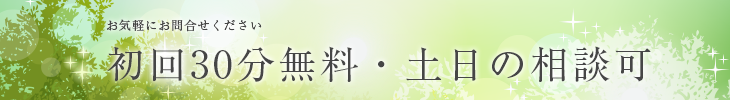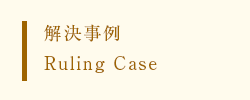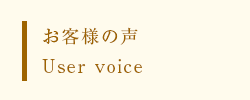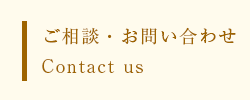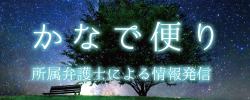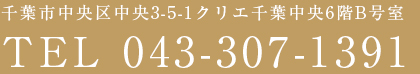法人破産・経営者保証ガイドライン
株式会社帝国データバンクの倒産集計によれば、2024年12月現在で、倒産件数は32カ月連続で前年同月を上回り、連続増加期間は1990年10月-1993年4月(31カ月)を超えて過去最長となっています。また、態様別にみると、『清算型』倒産が全体の97.2%を占め、規模別にみると、負債「5000万円未満」が最多になっているようです。
事業者の倒産の中には、個人事業主の倒産と法人の倒産がありますが、このうち法人が倒産する場合には、経営者が法人の主債務について連帯保証しているケースがほとんどであるため、経営者の保証債務の整理が同時に問題となります。
「経営者保証」には、経営への規律付けや資金調達の円滑化に寄与する面がある一方、経営者による思い切った事業展開や早期の事業再生、円滑な事業承継を妨げる要因となっているという指摘もあります。そのため、これらの課題の解決策として、全国銀行協会と日本商工会議所が「経営者保証に関するガイドライン」を策定しています(平成25年12月5日公表、平成26年2月1日適用開始)。
同ガイドラインを利用することで、法的手続である破産を選択せずに、また、債権者の方々の合意を得ることで、破産手続よりも多くの財産を手元に残して保証債務を整理することができる可能性があります。
弊所では、法人の倒産処理に注力しており、また、経営者の保証債務の整理についても経営者保証に関するガイドラインをファーストチョイスとしています。経営者を安易に破産させずに、再チャレンジのお手伝いができればと考えていますので、お気軽にご相談ください。
経営者保証に関するガイドラインを利用することのメリットには、以下のようなものが挙げられます(④で注意点も挙げておきます)。
【ガイドライン解決事例】